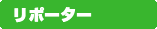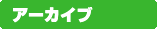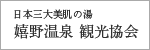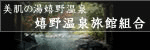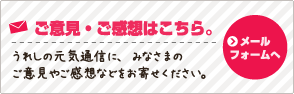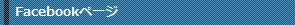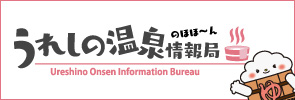| 前へ | 次へ |


 2013/02/23
うれしの元気通信第19号
2013/02/23
うれしの元気通信第19号
嬉楽里この人
ツイート
224porcelain 辻 諭さん
肥前吉田焼を全国区の陶磁器に

嬉野の静かな山あいにある吉田地区で作られている「肥前吉田焼」は、「うれしの茶」と並ぶ嬉野の名産品の一つ。400年を超える伝統と技術が今に受け継がれ、十数軒の窯元が創作活動を続けています。
その中に、柔軟でモダンなスタイルの吉田焼を発信し、注目を集めている人がいます。
辻与(つじよ)製陶所の7代目候補で、「224 porcelain(ニーニーヨンポーセリン)」を立ち上げた辻諭(つじ・さとし)さん(33)。
組み立てると小さな家になる箸置き、おにぎりの形で海苔の部分にしょうゆを入れる小皿など自由な発想で楽しく、つい手に取りたくなる磁器を作られています。
歴史とモダンを融合させ、挑戦を続けられている辻さんに話を聞きました。(ゆっぴー)
◆肥前吉田焼と辻与陶製所 与山(よざん)窯の歴史を教えてください。
◆肥前吉田焼は1577年、吉田の川で日本最初の磁鉱石が発見され、1598年に鍋島直茂が朝鮮陶工に吉田山で磁器を焼かせたのが始まりです。ただ、400年以上の歴史の割に、「吉田焼」の名はあまり知られていませんでした。それは、鍋島藩で作られた焼き物は昔、「有田焼」と呼ばれ、「吉田焼」の名前が表に出ることが少なかったからです。しかしその間、吉田焼の窯元は有田焼の大外山として技術を磨き、伝統を受け継いで今に至ります。辻与製陶所 与山窯も、安政年間(1854年~1859年)に初代与介が窯を開いており、私の父、賢嗣が6代目になります。160年の歴史がある窯です。
◆窯業を志したきっかけは。
◆幼い頃から焼き物が好きで、職人さんの仕事を見たり、仕事場の粘土で恐竜を作って遊んだりと焼き物に触れて育ちました。自然にこの仕事に就いたという感じですね。
◆辻与陶製所とは別に、「224 porcelain」を立ち上げられたきっかけを教えてください。
◆焼き物に携わってみて、「嬉野」や「吉田焼」の名を広く知ってもらいたいと思うようになり、吉田焼の特徴は何だろうと考えました。焼き物のブランドには、もともとその焼き物が持つ独自の伝統様式があります。有田焼の絵付けなどがそうであるように、様式があることで焼き物のブランドは認識しやすくなります。しかし、吉田焼には伝統様式がありません。ただ、様式がないことをマイナスと考えず、「吉田焼の様式がないのなら、逆に自由にやっていっていいのではないか。面白いものができるのでは」と考えました。まずは「224 porcelain」で面白いものをやろう。そう思ったのがきっかけです。
◆新しい取り組みですよね。苦労も多かったのでは。
◆それまでは作るまでが仕事だったわけですが、「224 porcelain」では企画、デザイン、生産、出荷、営業、そして販売までトータルでやっています。これに加え、辻与製陶所の仕事もあるため、本当に時間が足りません(笑)。でも、自分でお客さまに販売することもあるので、反応を直接見ることができます。おにぎりの小皿など商品を説明している時、「かわいい」とか「面白い」とか笑ったり、喜んだりしてもらえます。その瞬間を見られるのは、とても嬉しいですね。
◆嬉野の魅力をどう感じていますか。
◆嬉野は温泉、お茶、焼き物、自然など地域資源に恵まれた魅力的な町です。こんなにいいものがある町は珍しいと思いますし、仕事で嬉野に来てくれた人たちからも、そう言われます。その魅力をどう伝えるかが大事で、見せ方、出し方を変えていくだけだと思います。東京の知人と嬉野茶、うれしの紅茶、お酒、お米など嬉野の名産品をミニサイズにし、パッケージを変え、お土産にちょうどいい女性向けの新しいブランドを製作中です。そうやって異業種でも同じ思いを持つ人たちと何か新しいものに挑戦すると、嬉野でももっと面白いことができるのではないかと思っています。
◆最後に、これからの目標を聞かせてください。
◆「吉田焼って面白いものがあるよね」と言ってもらえるものを作っていきたいです。そして、吉田焼と「224 porcelain」の商品を一人でも多くの人に知ってもらい、喜んで使ってもらえたら嬉しいですね。
そんな「224 porcelain」で扱われている商品の一部を紹介します。
いくつかの箸置きを組み立てると...小さな家の置物に。
家の形の一輪挿し
ダイヤ彫シリーズ
レザーカバーを付けたカップ
224porcelainではホームページより商品の購入が可能です。
詳しくは ⇒http://www.224porcelain.com/ へジャンプして下さい。
ゆーど作:はなぶんことゆっつらくん
| 前へ | 次へ |