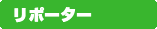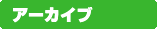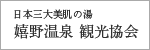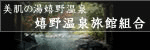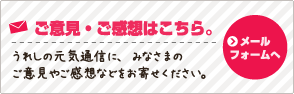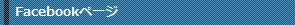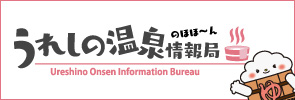| 前へ | 次へ |


 2012/10/12
現代喫茶人の会(Japan Tea Club)牛の岳へ
2012/10/12
現代喫茶人の会(Japan Tea Club)牛の岳へ
ツイート
10月9日(火)
特定非営利活動法人(NPO)
現代喫茶人の会の方々が嬉野にみえられました!
この日は嬉野の上不動地区にある「牛の岳共同茶工場(釜炒り茶モデル工場)」に新しい炒り葉機が入った日でもありその機械にも興味津々の皆様。最新の機能をもち、処理量は前のものの2倍だそうです!
ちなみに開発されたのは嬉野の機械メーカーさん。
工場内に入るとお茶のいい~香り(*^0^*)
牛の岳釜炒り茶モデル工場の北野等組合長にお話を聞きました。後ろにあるのが新しい炒り葉機。
牛の岳工場は5人の共同工場で、もともとは蒸し製の茶をつくる工場だったそう。今は釜炒り茶の工場です。
「新しい機械の処理量は前のものに比べ2倍になり、茶の最盛期は徹夜続きだったが今からは何日か徹夜が減ることを期待しています」と話されました。新茶の時期は夜中も製茶工場は動いています。何日も徹夜されていたのですね(>_<)
加工途中の茶葉の香りをかぐ現代喫茶人の会の濱島さん。
現代喫茶人の会の常務理事である濱島さんは「釜炒り茶というお茶に初めて出会ったのが太田(重喜)さんのお茶でした。こちらの釜炒り茶は飲んだ後で健康的な甘さが残り、お茶の香りも太陽を浴びた茶葉が想像できるような太陽の香りがしますね」と話されました。
味に関する表現が豊かですごく勉強になりました!実は濱島さん、有名な某雑誌の編集長をされていたとのこと。
ところで、
◆「釜炒り茶」って?
日本茶の起源とうれしの茶の歴史を感じる、生産量が嬉野茶全体の5%ほどと限られており希少価値の高いお茶です。伝統製法をそのままに、茶葉を直接直火で炒りながら造ります。丸みを帯びた茶は、蒸し製玉緑茶と比べて多少大きく、釜炒り特有の艶があり焙じ香がさわやかで喉ごしがさっぱりとしたお茶です。
「釜炒り茶」発祥の地とされる嬉野町は、明(現在の中国)から焼き物の文化とともにもたらされたとされ、約500年前の1504年に陶工(陶磁器の製造をする人。陶芸氏)である紅令民が明から釜を持ち込み、南京釜による炒葉製茶法を伝えたことが、嬉野式の釜炒り茶の始まりとされています。
(JA佐賀ホームページより)
釜炒り茶は嬉野の代表的なお茶で、歴史あるお茶の一つです。
今年は全国茶品評会で4年連続
蒸し製玉緑茶とともに
農林水産大臣賞及び、産地賞に輝きました!
釜炒り茶をつくる工程は・・・
1、茶葉を直接加熱した釜で炒り、酸化酵素の活性を失わせる
2、揉捻(じゅうねん)・・・茶葉を揉む
揉捻機の近くに行くといい香り~(>▽<*)円を描くように回転していました。
3、揉捻した茶葉を直接加熱式の水乾機で乾燥する
4、締炒り機(直接加熱)で丸型(玉型)に整形する
5、熱風で含水率4~5%まで乾燥させる
お茶を愛する方々と出会って嬉野茶のファンが全国各地にいらっしゃることを身近に感じました(*^▽^*)うれし~のな一日でした♪
| 前へ | 次へ |