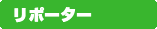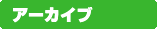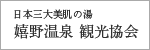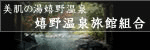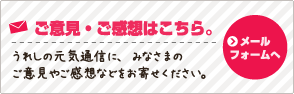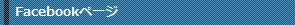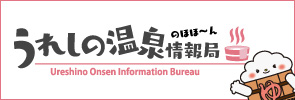| 前へ | 次へ |


 2012/07/19
焼き物作りの「裏側」がみれる!? 「志田焼の里博物館」
2012/07/19
焼き物作りの「裏側」がみれる!? 「志田焼の里博物館」
ツイート
「志田焼」とは、塩田町で作られていた陶磁器。
1700年頃にはもう作られていたといわれています。
主に民衆向けで
最初は、陶器を作っていましたが
次第に磁器の焼成、大中小の絵付皿
昭和30年ころには大量生産で火鉢などが作られました。
その工程を
分業ではなく「全工程を一つの工場で製造」していた、しかも23棟もある大規模な工場を
道具も備品も
そのまま保存したのが「志田焼の里博物館」です。
「そのまま!」 です(^^)
大正3年から昭和59年まで使われていた工場自体をを博物館へ
近代化遺産にもなっている貴重な理由は
1.全工程が同じ敷地内で見られる!全国でも稀(たぶんここだけだろうとのこと)
2.大窯、道具、機械、壊れたイス!?など当時のまま保存!!
建物群自体、備品だったもの全てが貴重な展示品なんです。
今回は、青木館長じきじきに説明してもらいました。
「志田焼の里博物館」の歴史や陶器、磁器などを
教えてもらい陶磁器作りの説明へ(*^_^*)
まずは、
石を砕くのですが、
その石も自分たちで船を所有し、
天然で磁器になる天草石を天草から塩田まで運んできていたそうです。
「その為の船を持っていた焼き物の会社」だったのです。すごい!
その石を
大きい機械を使って粉砕します。
石の粉末が舞い上がるので
マスクをしての作業です。
攪拌機の水槽に砕いた石を入れ、水槽の水の上に濁った水を移して細かい砂状になった石を沈殿させます。
そして、絞り機にかけます。この工程を水簸(すいひ)といいます。
【絞り機です わかりづらいですね^_^;】
絞り機の木枠へポンプでおくって圧をかけて脱水します。
できた陶土はねかせて粘りをだして
成形しやすくします。
釉薬(上薬)が入っているカメ。
素焼きの陶磁器にかける薬。
焼成するとガラス質になって光沢がでます(^-^)!

【おっきくてテンションあがってます^_^;】
この大きなカメを作れるのも100mの大きなのぼり窯があったから。
4~5人で運ぶ大きさ。
なかなか作れないBIGさです(◎o◯;)
流し込みの型。
それまでは、ひとつひとつ「ろくろ」で作っていました。
この「型」は青木館長いわく「革命的」だったそう。
このやり方が出来たから大量生産が可能になり、工場も大きくなったのです。
使われていた道具も当時のまま。
古――いオロナインの瓶もありました^_^;
【焼成場 大窯の中。】
くわしくは・・「むちゃくちゃ大きい!!石炭大窯」へ
・・ほんと大きかったです\(◎o◎)/!
初期~昭和までの志田焼が並んでいます。
左の写真、手前は湯たんぽです。
軍用食器も作っていました。
敷地内には、ランプシェードなどの体験ができます。
経済産業省の「近代化産業遺産」にも認定されている博物館。
作る全工程を見学でき、
貴重な23棟の建物と約1万点の展示品で
志田焼・焼き物作りの「裏側」を知ることができます(*^_^*)
【志田焼の里博物館】
〒849-1402 佐賀県嬉野市塩田町久間乙3073
TEL・FAX 0954-66-4640
Open 9:00~17:00
定休日・・水曜日 年始何末
入場料 大人300円 小・中学生 150円
| 前へ | 次へ |